WHOの『世界自殺予防デー』とは
『世界自殺予防デー』とは、WHO(世界保健機関)が毎年9月10日を「World Suicide Prevention Day」とし、全世界を挙げて、自殺予防の取り組みをしようと提唱している日です。WHOでは自殺予防の意識を全世界的に高めるべく、自殺に関するさまざまなデータの公表や、自殺予防のために、どのような取り組みが必要なのかの情報をホームページなどで公開しています。
それに応える形で、世界各国が毎年9月10日を中心に自殺予防のための積極的な対策を展開しており、日本では9月10日から9月16日を「自殺予防週間」とし、国および地方公共団体が自殺予防のための啓発活動や、心の相談などを強化する期間と位置付けています。
WHOが自殺予防に力を入れている背景
WHOの統計データによれば、世界では年間100万人あまりの方が自殺しているとされます。40秒に1人の割合で、地球のどこか自殺しているという計算です。さらに自殺未遂にいたっては、その「20倍」の件数が報告されています。
自殺未遂は医療機関や警察からの報告、本人などからのアンケート調査などによって出てきた数字に過ぎず、申告されていない例も含めれば、もっと多くの数にのぼることでしょう。
また、世界の自殺率は、過去45年間で60%も上昇しており、世界の人々の健康的な生活を目的にするWHOにおいては、見逃すことができない由々しき事態となっています。
自殺する人の傾向としては、これまでは高齢の男性が多かったのですが、近年では若い世代の自殺が増加傾向にあります。15歳~44歳までの若年層と45歳以上の自殺者の割合は、過去50年間で逆転しました。
では、自殺の原因は何だったのでしょうか。
ヨーロッパや北米では、うつ病やアルコール依存症といった精神疾患が引き金となっているのに対し、アジア圏では衝動的な要因が多くなっています。なお、世界の自殺率マップにおいては、10万人あたり13人を超える地域をレッドゾーンで警戒地域にしていますが、日本もレッドゾーンに該当している点は見逃せません。
WHOが提案する自殺予防の手段
自殺を予防するためにWHOは以下ようなコミュニティレベル、国家レベルでの5つの対策を講じることで、自殺の多くを防ぐことができるとしています。
第一に、自殺に利用されやすい道具、たとえば、銃や薬物、農薬などに簡単にアクセスできないようにすることが挙げられます。これは企業などにも求められることで、販売するにあたって本人確認や目的を確認するなどして、簡単に手に入らないようにすることが必要です。
第二に精神疾患、中でも自殺につながりやすい、うつ病やアルコール依存症、統合失調症の患者の治療に力を入れることが求められます。
第三に自殺未遂を起こした人の経過を追跡調査し、その後も似たような未遂行動に出ているのか、自殺願望を持ち続けているのか、それとも健康な心理状態を取り戻したのかを解明することも大切です。特に自殺願望がなくなった方の場合、何が影響を与えたのか、周囲や社会的なサポートがあったとすれば、どのような手段が有効かを分析することで、自殺予防へとつなげることができるからです。
第四にメディアに対して、責任ある報道を求めています。WHOでは別途、自殺報道ガイドラインを策定しており、自殺を巡る報道にあたって報道機関がやってはいけないこと、逆に行うべきことを定めています。
第五に医療従事者を訓練し、自殺に至りやすいメンタルヘルスに不調を抱えている方や精神疾患患者への適切な対応、自殺に至った患者が救急搬送されてきた場合の対応などを深めていくことも必要です。
いち個人や企業にとっての『世界自殺予防デー』
日本では自殺対策基本法において、WHOの世界自殺予防デーである9月10日をスタート期日として、9月16日までを「自殺予防週間」と位置付けています。国や地方公共団体から国民一人ひとりへの呼びかけとして、新聞やテレビ、ラジオ、インターネットのポータルサイトやニュースサイト、SNSなどコミュニティサイトを運営する企業への協力を得ながら、自殺や精神疾患などに対する偏見をなくし、正しい知識を伝え、孤立・孤独を防ぐことが自殺予防対の有効な手段であることを伝えています。
国民一人ひとりが自分の周りにいるかもしれない自殺願望を持つ人に気づいて、声をかけ、話に耳を傾け、必要に応じて相談窓口につなぎながら、見守っていく「ゲートキーパー」としての意識を持つことも大切です。
民間企業の中にはゲートキーパーとしての役割や対処法を学ぶためのセミナーを企業の人事や管理職向けに開催する場合やフォーラムなどを開催して自殺の未然予防に取り組んでいるケースもあります。
厚生労働省は「こころの健康相談統一ダイヤル」や「よりそいホットライン」の連絡先の周知徹底を実施し、国民の約3人に2人以上が当該相談電話について見聞きしたことがある状態にすることを目指しており、報道企業でもその周知が行われるようになりました。

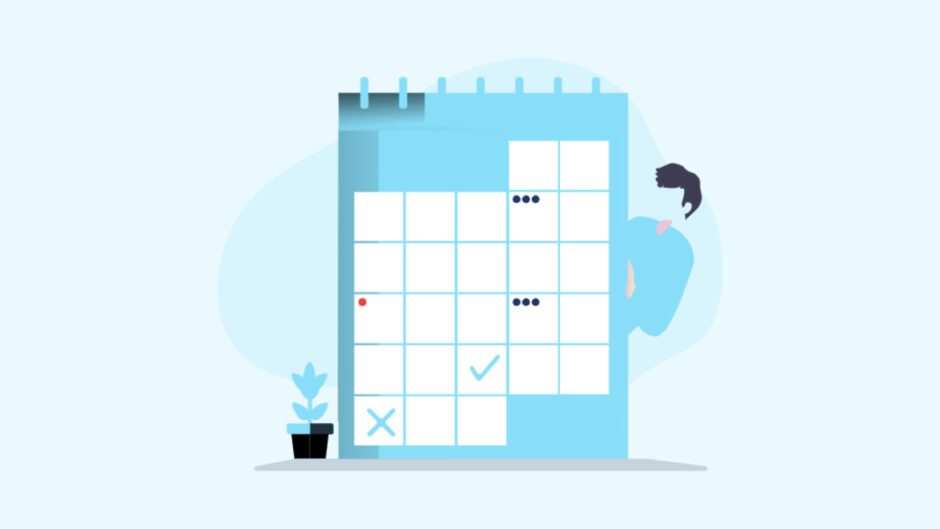



WHOの『世界自殺予防デー』と日本での取り組み – パパゲーノCEOブログ
[url=http://www.g65j50832dmc42e099g8vs7vu4igq1mms.org/]ughikrrdws[/url]
aghikrrdws
ghikrrdws http://www.g65j50832dmc42e099g8vs7vu4igq1mms.org/